
「ワケあり物件」のマイナス要素を魅力に変える方法PART2【POINTは〇〇〇の需要をつかむ】



(質問)弊社は、賃借人Aとの賃貸借契約において、Aが賃料保証会社に保証委託すること、そして賃料は賃料保証会社からの振り込みとするという特約を設けていました。
しかし、Aは、賃貸借契約を締結して間もなく、保証料の負担を嫌うようになり、保証会社との保証委託契約を解約して、賃料を直接弊社に振り込んできました。
そして、Aは、弊社が振り込みを拒絶すると今度は供託するなどして、弊社との対話にも応じません。
弊社としては、Aとの賃貸借契約を解除したいと思いますが、可能でしょうか。

コロナ禍で、在宅で仕事・勉強・趣味・買い物等を行う時代となり、住まいへの考え方やニーズに変化が出ています。
続きを読む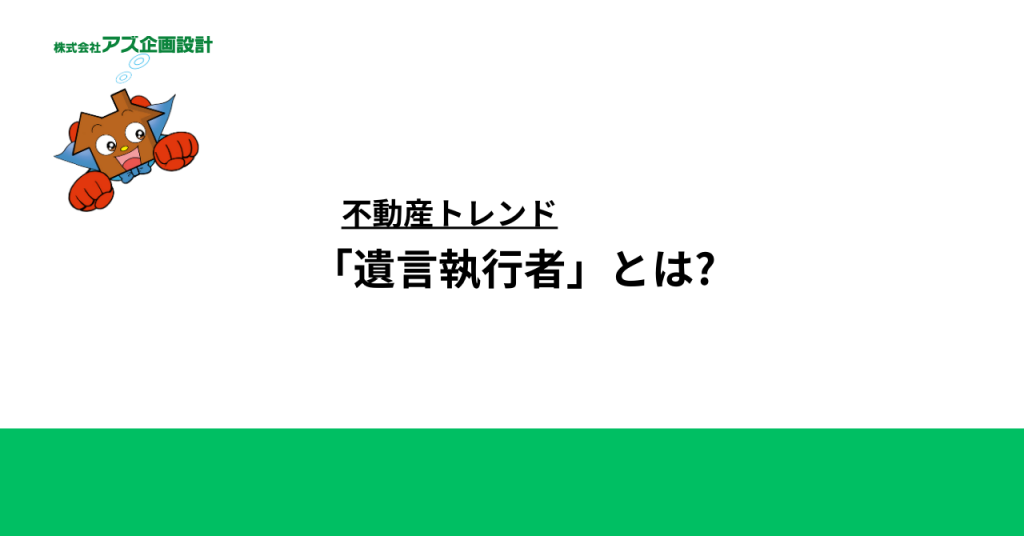
「最近亡くなった独身の叔母が遺言書を残していたことが分かりました。遺言書では遺産の分配についてだけでなく、私を『遺言執行者に指定する』とも書かれていました。私は何をしなければならないのでしょうか?」などという相談が司法書士事務所に持ち込まれることがあります。今回は「遺言執行者」について解説します。
遺言書の効力が生じるのは遺言者が亡くなったときです。当然のことながら、遺言者自身は相続発生後に遺言書の内容の実現を図ることはできません。そこで、遺言者は遺言書の内容に従った相続を実現するために、必要な手続を行う「遺言執行者」を遺言書で指定することができます。民法上、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」、「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」とされています。遺言執行者は非常に強い権限を持っているのです。
遺産相続の手続は、預貯金の解約も、又は不動産登記手続も、たくさんの戸籍だけでなく、相続人全員の実印と印鑑証明書の提出を求められることが多く、これに非常に手間がかかります。この点、遺言執行者がいると、遺言執行者の実印と印鑑証明書があれば、ほぼ全ての手続を進めることができます。遺言書の内容に不満がある相続人や手続に協力的でない相続人がいるような場合でも、遺言執行者が単独で相続手続を進めることができるので、全体の事務負担を軽くし、より円滑に相続手続を進めることが可能になるのです。
ただし、遺言執行者は①遺言執行者に選任された旨を相続人全員に通知し、②財産目録を作成して全ての相続人に開示し、③相続財産を注意して管理し、④相続人へ進捗や完了を報告する、等々の重要な義務を負っています。経験がない家族や親族が遺言執行者に指定された場合、日常の仕事や家事の片手間でこれらを行うのは決して簡単なことではありません。 遺言執行者を弁護士や司法書士等の第三者に依頼すると、相続人の諸々の負担を大きく減らすことが可能です。手続の透明性が確保されて、相続人間の無用なトラブルを防ぐことにつながる場合もあります。遺言者が遺言書で直接弁護士や司法書士を指定しなかった場合であっても、相続発生後、遺言執行者に指定された家族や親族が、遺言執行の任務を第三者に行わせる方法や家庭裁判所にあらためて遺言執行者選任の申立をする方法もあります。遺言書や遺言執行者について何かお悩みの方は弁護士や司法書士への相談をお勧めします。

皆様こんにちは。住宅・不動産・土地活用・不動産投資のコンサルをおこなっていますコミュニケーションバンクの山本です。
土地の有効活用には、建ぺい率・容積率を最大限に活かすことがポイントになります。容積率には緩和措置があり、ロフト・小屋裏収納(屋根裏部屋)・地下室・バルコニーは、それぞれ細かい制限がありますが延床面積に入りません。このような空間・スペースは、賃貸入居者に、収納・書斎・ベッドスペース・備蓄庫として利用いただけますし、地下室はオーディオルーム・防音スタジオなどとしても人気があります。
コロナ禍で、仕事も勉強も趣味も家で過ごすことができることがお客様のニーズにあります。災害に備えた備蓄庫も欲しいし、収納スペースもますます必要になります。でも大家さんとしては、大きな部屋をつくると貸せる部屋数が減ってしまいます。
皆様の土地活用、老朽化アパートの建て替えの際に、土地や建物の能力を最大限に利用いただけるようご提案したいと考えています。
空間利用の例として、ベッドスペースの下にワークスペースをつくることができる会社があります。楽しそうな空間ですね(セレコーポレーションさん資料から)。
また、アズ企画設計主催の不動産情報交換会に良く参加しているミサワホームさんが、収納で差別化できるアパートを展開しています。
天井高を抑えつつ、1階には蔵という収納スペーススキップマルチルーム、2階にもスキップマルチルームを設けてくれます。スキップマルチルームで、仕事や遊ぶことが自由にできます。収納率:1階約16%、2階約11%を実現しています。*プランにより異なります(賃貸マンション平均収納率約8%)。2階のロフトだけでなく、1階にも空間を多くつくることで、1階の空室リスクを抑えることができます。
皆様のアパートはどれくらい空間利用ができているでしょうか?このような空間設計は最初が肝心です。後から付け加えることはかなり難しいと言われていますので、建築計画がある大家さんには是非提案を受けていただきたいです。
ご興味がある方は、アズ企画設計様にお問い合わせください。私からご紹介申し上げます。
また、老朽化アパートを所有していて、売却にご興味があるかたも、事前調査を無料で行いますので、是非お問い合わせください。
それにしても、アズ企画設計不動産交流会は本当に宝の山です。不動産会社の皆様には参加をお勧めします。