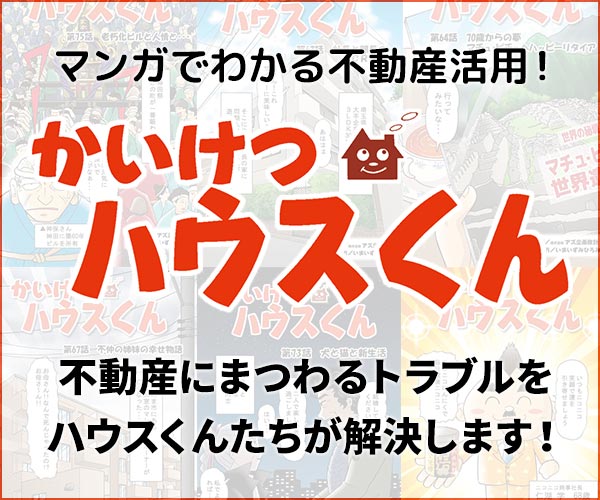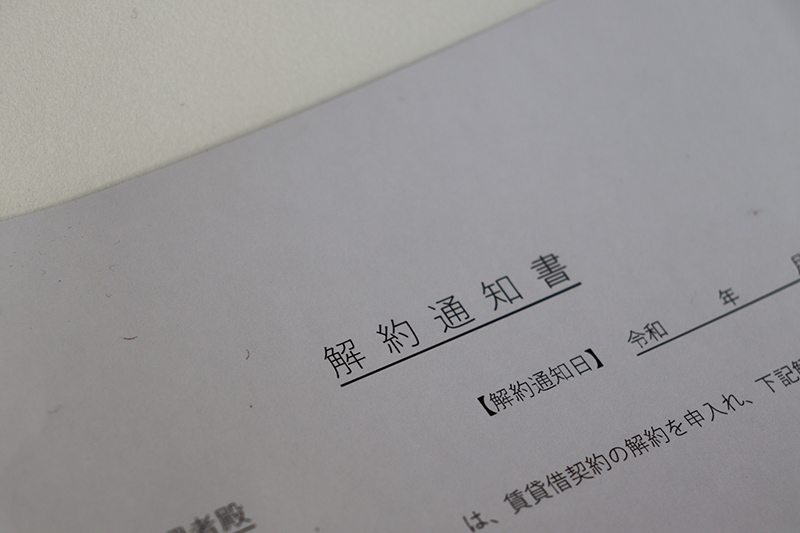
弊社は、一昨年、A社にオフィスビルのワンフロアを期間5年として賃貸(普通賃貸借)しましたが、契約書には賃借人からの中途解約の条項はありません。最近、A社は、「コロナ禍」でのテレワークによりフロアが過大となったなどとして賃貸借の中途解約を申入れてきました。しかし、弊社は、期間5年の内の残りの期間の賃料収入を見込んでいます。A社の中途解約の申入れに対してどう考えればよいでしょうか。
(回答)
期間の定めがある賃貸借契約において、賃借人から中途解約できる旨の条項がある場合も少なくなく、その場合は、賃借人は、賃貸人に対して期間の途中で解約申入れをして契約を終了させることができます。
他方で、貴社の契約のように、期間5年との定めがあり賃借人からの中途解約の条項がない場合に、賃借人は、賃貸人に対して期間の途中で解約申入れできるのでしょうか。
これについては、取引慣習上認められるとの考え方もあるようです。しかしながら、土地の賃貸借契約の例ですが、最高裁昭和48年10月12日判決は、賃貸借契約における期間の定めは、特段の事情のない限り、賃貸人賃借人双方の利益のためにあり、賃貸借契約において期間が定められている場合は、解約権を留保していない当事者が期間内に一方的にした解約申入れは無効である、と判示しています。つまり、賃貸借契約の期間の定めは、その間は使用収益できるという賃借人の利益のみならず、その間は賃料収入を得られるとの賃貸人の利益にもなります。そこで、賃借人からの解約申入れの定めがない以上賃借人からの中途解約は認められない、というのが判例の考え方です。
これは建物賃貸借にも当てはまるでしょう。現に、東京地裁平成23年5月24日判決は、建物賃貸借の事例で、期間の定めがある賃貸借契約においては、当事者が期間内に解約する権利を留保し、あるいは期間内でも一定の要件の下で解除できる旨の合意をしているのでなければ、一方的に期間内に解約申入れをすることはできないと判示しました。そして、賃借人による解約申入れは、賃貸借契約を終了させる効力がなく、契約は依然として存続している、と判示しています。
そこで、貴社としては、A社の解約申入れを認めず、賃貸借は継続しているとして、A社に対して期間満了まで賃料請求をすることが法的には可能です。
ただ、A社があくまでも契約の終了を主張して鍵などを返却して退去した後に、A社に対して賃料請求を続け訴訟提起までするのは、訴訟コストをかけてその間は対象フロアを稼働させない状態におくこととなるので、あまり得策ではないでしょう。たとえば、残存期間の賃料の支払ではなく、新たなテナントが入居したときまでの賃料の支払を条件にA社と和解するのも方法です。